先日、「歴史」をテーマにした本を持ち寄る読書会に参加した。
一言に歴史をテーマにといっても、さまざまな角度から、いろいろなテーマを扱った本がある。
どんな時代にも、人は誰もが「幸せ」になりたいと思って生きている。
その一人一人にとって、「幸せ」とはどんなものなのか?
その「幸せ」を目指して、人は何を考え、どう動いたのか。
結局のところ、人の歴史は、その集積だ。
パリへの旅から戻ってすぐに、映画館で「パリよ、永遠に」を見た。
第二次大戦末期。すでにドイツの敗戦は予想できる時期、パリはドイツ軍に支配されていた。
「パリを明け渡すなら、その前にパリのすべてを爆破せよ」
ヒトラーの命令を受けて総司令官をつとめるコルティッツ。
命令に従わなければ自分だけではなく家族も処刑されると知っている。
パリ生まれパリ育ちの、中立国スウェーデン総領事ノルドリンクは、
パリを燃やすなと説得にのぞむ。
この二人の緊迫したやりとりが映画のほとんどを占める。

同じ時期のパリを扱った1966年(実はコルティッツの没年でもある)の映画「パリは燃えているか」のDVDを見た。
高校の時から持っている「世界映画名作全史」という本には、見た映画にチェックを入れている。実はこの映画も私は高校生の時にすでに見ているはずなのだ。だが、タイトル以外まったく記憶になかった。
改めて見てみると(ポスターはカラーだが、実際はモノクロ映像)、「パリよ、永遠に」に比べると、もう少し広くこの時期を扱っており、レジスタンスの党派同士の争いや、ドイツ軍と連合軍との戦闘場面、連合軍をパリへと要請する際の逸話などもあり、全体としては一人一人の人としての思いやその中での決断といった個人的なストーリーは薄まっている。
(監督は「禁じられた遊び」や「太陽がいっぱい」のルネ・クレマン、制作は「ベン・ハー」の脚本も手がけたゴア・ヴィダルとコッポラ。出演者は、オーソン・ウェルズ、ジャン・ポール・ベルモンド、アラン・ドロン、カーク・ダグラス、イブ・モンタン、シャルル・ボワイエ、チョイ役でジョージ・チャキリスやシモーヌ・シニョレなど、超豪華な配役。ベルモンドもドロンも英語を話しているのがなんとも、、なんだけれど)
私たちはいつも実は岐路に立っている
1966年からすでに50年近くを経ても、3時間近い長尺の映画を見てしまうほどの魅力はある。とはいえ、やはり、現代的な視点は「パリよ、永遠に」なのだろう。
最後までパリ爆破の命令を出さないまま、コルティッツは降伏し捕虜になる道を選ぶのは史実なので、どちらも共通。「パリよ、永遠に」では絶対的な命令と個人の思い、人として何をすべきかという信念との間で揺れ動く「個人」がより丁寧に描かれている。
人生の岐路にたって、人は何を思い、どう動くのか。
コルティッツほどの岐路に立たされる人間はそうはいない。
だが、私たちは気づかなくても日々常になんらかの岐路に立ち、進む道を選んでいるのだ。その積み重ねが今日の自分を作っている。
映画2本を見て、そんなことを思う今日。
 サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist
サカイ優佳子
Yukako Sakai
Food Activist































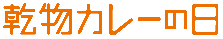






コメントをお書きください